http://www10.plala.or.jp/kanbuniinkai/ http://kanbun-iinkai.com http://3rd.geocities.jp/miz910yh/ http://kanbuniinkai7.dousetsu.com http://kanbuniinkai06.sitemix.jp/ http://kanbuniinkai.web.fc2.com/ http://kanbuniinkai12.dousetsu.com/ http://blog.livedoor.jp/kanbuniinkai10/
漢詩総合サイト

杜甫李白を詠う
・贈李白[五言律排]
・贈李白[七言絶句]
・遣懐
・春日憶李白
・飲中八仙歌
・昔游
・冬日有懐李白
李白杜甫を詠う
はじめに
杜甫の人生は詩に向かって、まじめに生きた人生です。生きるための術はなるようになる自分の詩は世界一だ。くじけない、めげないものでした。
杜甫には、たくさんの詩が残されており、しかもそれらが註者らによって、年経過順に並べられていること、読んでいくと、杜甫のおかれている状況、杜甫の考えが見えてきます。このページではj十数種の作品を見ながら物語を始めます。
それでは杜詩を深く理解することはできません。のち、200首前後の「ものかたり」を紹介する予定です。
杜詩は、自身の誠実さが息を引く最後まで続いている。人間として見ても杜詩を読んだ人の心に、深く、新しい感動を残してくれる。杜詩は時間空間を超えて人の心にあるものを引き出してうたってくれています。熟読をすればするほど、繰り返せば繰り返すほどひきつけられていきます。
杜甫の詩は常に進化していきます。庶民、人々に対する気持ち、朝廷に対する気持ち、政治的な語り、白髪の表現法の変化、妻子に対する表現、それらすべて、味わいが深まり、詩の風格が進化しているのです。
杜詩はまず、青年期、若い希望に満ちた詩を残しています。でもなぜか杜甫は士官に対し本気心が伝わりません。多くの詩人たちがそうであるように、王維にしても十代のころから士官を目指します。そして、落第した孟浩然ほか多くの文人たちは四十を境に士官をあきらめ故郷に帰ります。
杜甫の場合はこれが当てはまりません。この疑問を抱かせるのはまず、官吏の中であまり評判のよくない人物たちとの交遊です。次に、士官活動を懸命にやり始めたのが、李林甫に権力集中されてからなのです。文人を徹底的に排除した有名な宰相です。及第させない宰相のもとで、どんなに有力なコネクションでも通じなかったのです。
そこで、妻子を実家に預けます。そための寒い厳しい旅、敵の目を盗んで死ぬ思いで脱出したこと。
いろいろな苦しい出来事、自分が置かれた立場から見ると庶民の苦しい生活をほっとけない、そのためにその状況を詳らかに詠います。一方、目指していた士官がかなわない。
最高の華やいだ気持ちの詩があります。あまり有名ではないのですが一首だけあります。しかし、この最高点から一気に「官を辞す」事にします。ここから杜詩はガラッと変化していきますが、この時期の変化の激しさはすさまじいものです。秦州で過ごす間までに、朝廷からの召喚を期待していました。
召喚がないとわかって、杜甫は、後になって二度としたくないといった同谷紀行、成都紀行を経て、成都浣花渓に草堂を新築します。過去の文献でこの時期最も安定した時期といわれていますが、ここでも戦火が近まり、長江を下って、菱州に船でむかいます。
菱州では猛烈なスピードでそれまで書き溜めた詩賦を整理し、その上、新たな詩をたくさん書いています。そして、叛乱によりここでも長居はできません。さらに南下し漂泊の中で死を迎えます。
士官かなって最高潮の気分までの時期、最高時から秦州から同谷紀行に旅立つまでの時期、2紀行時期、成都浣花渓での時期、菱州寓居を中心にした時期、そこを旅たち、漂泊の中で詩を迎えるまでの時期、ということになります。これを杜甫の詩の違いによって、分けると次の通りです。
1.青年期、
2.就活期、
3.安史の乱による激動期、4.人生至福から奈落の時期、
5.秦州発までの時期
6.同谷・成都紀行
7.成都浣花渓草堂
8.菱州寓居、
9、漂泊の旅の中で
ここでは、その時期と年齢を追って杜甫の人生を見ていきましょう。
一般的区分は①青年期と士官を目指す時期
②安史の乱翻弄期
③成都での安定期
④南国漂泊期 というものです。
ただ、このページでは、9つに区分しますが、大別すると、杜甫のエポックメーキングは、一般に言われる4時期ではなく「ひとつ」です。前の9区分でいう4の時期にあたります。
このことについては別の講でふれたいと思います。(杜甫私記)
杜甫の物語としてとくに青年期において「壮遊」「昔遊」などが用いられますが、
昭和の杜詩研究の第一人者、吉川幸次郎がその著書『杜甫私記」第1巻昭和25年3月15日発行で「もはや『壮遊』の詩のみによって、長安十年の生活をを語るべきでない。」直接杜甫の描いたいろいろな詩によってのみ語るべきである。
このページはそれに従っているのは言うまでもない。しかし吉川氏は杜詩を4時期に区分されるとしています。ここではそのことを指摘しておくのみとし、このサイトに示す杜甫私記にエポックメーキングについて述べたいと考えています。
杜甫李白を詠う
・贈李白[五言律排]
・贈李白[七言絶句]
・遣懐
・春日憶李白
・飲中八仙歌
・昔游
・冬日有懐李白
李白杜甫を詠う
はじめに
杜甫の人生は詩に向かって、まじめに生きた人生です。生きるための術はなるようになる自分の詩は世界一だ。くじけない、めげないものでした。
杜甫には、たくさんの詩が残されており、しかもそれらが註者らによって、年経過順に並べられていること、読んでいくと、杜甫のおかれている状況、杜甫の考えが見えてきます。このページではj十数種の作品を見ながら物語を始めます。
それでは杜詩を深く理解することはできません。のち、200首前後の「ものかたり」を紹介する予定です。
杜詩は、自身の誠実さが息を引く最後まで続いている。人間として見ても杜詩を読んだ人の心に、深く、新しい感動を残してくれる。杜詩は時間空間を超えて人の心にあるものを引き出してうたってくれています。熟読をすればするほど、繰り返せば繰り返すほどひきつけられていきます。
杜甫の詩は常に進化していきます。庶民、人々に対する気持ち、朝廷に対する気持ち、政治的な語り、白髪の表現法の変化、妻子に対する表現、それらすべて、味わいが深まり、詩の風格が進化しているのです。
杜詩はまず、青年期、若い希望に満ちた詩を残しています。でもなぜか杜甫は士官に対し本気心が伝わりません。多くの詩人たちがそうであるように、王維にしても十代のころから士官を目指します。そして、落第した孟浩然ほか多くの文人たちは四十を境に士官をあきらめ故郷に帰ります。
杜甫の場合はこれが当てはまりません。この疑問を抱かせるのはまず、官吏の中であまり評判のよくない人物たちとの交遊です。次に、士官活動を懸命にやり始めたのが、李林甫に権力集中されてからなのです。文人を徹底的に排除した有名な宰相です。及第させない宰相のもとで、どんなに有力なコネクションでも通じなかったのです。
そこで、妻子を実家に預けます。そための寒い厳しい旅、敵の目を盗んで死ぬ思いで脱出したこと。
いろいろな苦しい出来事、自分が置かれた立場から見ると庶民の苦しい生活をほっとけない、そのためにその状況を詳らかに詠います。一方、目指していた士官がかなわない。
最高の華やいだ気持ちの詩があります。あまり有名ではないのですが一首だけあります。しかし、この最高点から一気に「官を辞す」事にします。ここから杜詩はガラッと変化していきますが、この時期の変化の激しさはすさまじいものです。秦州で過ごす間までに、朝廷からの召喚を期待していました。
召喚がないとわかって、杜甫は、後になって二度としたくないといった同谷紀行、成都紀行を経て、成都浣花渓に草堂を新築します。過去の文献でこの時期最も安定した時期といわれていますが、ここでも戦火が近まり、長江を下って、菱州に船でむかいます。
菱州では猛烈なスピードでそれまで書き溜めた詩賦を整理し、その上、新たな詩をたくさん書いています。そして、叛乱によりここでも長居はできません。さらに南下し漂泊の中で死を迎えます。
士官かなって最高潮の気分までの時期、最高時から秦州から同谷紀行に旅立つまでの時期、2紀行時期、成都浣花渓での時期、菱州寓居を中心にした時期、そこを旅たち、漂泊の中で詩を迎えるまでの時期、ということになります。これを杜甫の詩の違いによって、分けると次の通りです。
1.青年期、
2.就活期、
3.安史の乱による激動期、4.人生至福から奈落の時期、
5.秦州発までの時期
6.同谷・成都紀行
7.成都浣花渓草堂
8.菱州寓居、
9、漂泊の旅の中で
ここでは、その時期と年齢を追って杜甫の人生を見ていきましょう。
一般的区分は①青年期と士官を目指す時期
②安史の乱翻弄期
③成都での安定期
④南国漂泊期 というものです。
ただ、このページでは、9つに区分しますが、大別すると、杜甫のエポックメーキングは、一般に言われる4時期ではなく「ひとつ」です。前の9区分でいう4の時期にあたります。
このことについては別の講でふれたいと思います。(杜甫私記)
杜甫の物語としてとくに青年期において「壮遊」「昔遊」などが用いられますが、
昭和の杜詩研究の第一人者、吉川幸次郎がその著書『杜甫私記」第1巻昭和25年3月15日発行で「もはや『壮遊』の詩のみによって、長安十年の生活をを語るべきでない。」直接杜甫の描いたいろいろな詩によってのみ語るべきである。
このページはそれに従っているのは言うまでもない。しかし吉川氏は杜詩を4時期に区分されるとしています。ここではそのことを指摘しておくのみとし、このサイトに示す杜甫私記にエポックメーキングについて述べたいと考えています。
漢詩総合サイト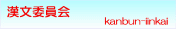
作品で語る、杜甫の人生
1.青年期、
遊龍門奉先寺
望 嶽
2.就活期
李白に遭遇する前
その後(長男が生まれて以降)
安禄山の叛乱を察知していた?
3.安史の乱による激動期
反乱軍に捕まる
軟禁の中で
脱出
4.人生至福から奈落の時期
5.秦州発までの時期
6.同谷・成都紀行
7.成都浣花渓草堂
8.菱州寓居、
9、漂泊の旅の中で
漢詩ジオシティーズ倶楽部
漢文委員会 fc2支部
作品で語る、杜甫の人生
1.青年期、
遊龍門奉先寺
望 嶽
2.就活期
李白に遭遇する前
その後(長男が生まれて以降)
安禄山の叛乱を察知していた?
3.安史の乱による激動期
反乱軍に捕まる
軟禁の中で
脱出
4.人生至福から奈落の時期
5.秦州発までの時期
6.同谷・成都紀行
7.成都浣花渓草堂
8.菱州寓居、
9、漂泊の旅の中で
| 杜甫のものがたり |
杜甫ものがたり

| 77 青年期 | 78李白と遭遇 | 158 若き思いで | 李白と別離後 |
| 李白を詠う12 | 81叛乱軍に捕縛 | 82左遷、苦悩 | 83官を辞すⅢ |
| 199三吏三別 | 84 秦州の詩 | 同谷・成都紀行 | 90成都草堂 |
| 92成都草堂2 | 雲南・菱州 | 漂泊・洞庭湖 | お問い合わせ |
1.青年期、
・ 18歳になると洛陽で盛り場に出入りし、遊んでいました。
このころまで朝廷では玄宗が即位して以降、張説が文人として節度ある政治をおこなっていました。もっとも周辺諸国に対しても小競り合いを含め100年くらいで大強国化したのは、太宗(李世民)、則天武后の政治力によるものが大きかった。都はこのころは、長安が首都ですが、則天武后は、洛陽でも半分過ごしたために、東の都としていました。洛陽も古い町で身分制、血筋を重んじる時代ですから、杜甫も自慢できる祖先をもつ関係で、洛陽で血筋の良い若者同士で遊んだようです。中国では唐時代の数百年前から律令体制であり、基本的に貴族は世襲されていた。文人や、軍人の採用に関しては試験と血縁、権力者、知識人を頼って登用されました。杜甫は試験より血筋と縁者を頼りにして、少し見下すところがあったようです。
開元22年(734)23歳呉越(江蘇・浙江)に遊ぶ。鞏県で郷試(ごうし)を受けて及第。
開元23年(735)24歳呉越より洛陽に帰り、進士の試験に応ずるも及第せず
開元24年(736)25歳試験で戻ってから1年余り洛陽で過ごします。蘇源明と洛陽の東南、伊河に臨む名勝龍門の奉先寺にて遊ぶ。龍門の奉先寺奉先寺は龍門最大の石屈寺院で、則天武后を模したという高さ17mの廬舎那仏は (761)に完成しています。石屈には数十年以上かかるとされていますので、杜甫が訪れたころは建設の途上であった。
遊龍門奉先寺
已従招提遊、更宿招提境。陰壑生虚籟、月林散清影。
天闕象緯逼、雲臥衣裳冷。欲覚聞晨鐘、令人発深省。
(わたしは今日このお寺さんに遊んだばかりではなく、さらにこのお寺さんの境内に宿ることにした。山の北側の谷には風がうつろな響きを立てて湧き起こり、月下の林には清らかな光が散乱している。
天の宮門かと怪しまれるこの山の上には星のよこ糸が間近に垂れ下がり、雲のなかに身を横たえていると着物も冷ややかに感ぜられる。目覚めようとするころに朝の鐘の音が聞こえてきたが、それは聞く者に深い悟りの念を起こさせずにおかない。)
この詩は杜甫のもっとも得意とする古詩です。これまで通常、詩は八句のうち前半四句を叙景もしくは叙事にあて、後半四句を感懐にあてる形式だったのですが、杜甫ははじめの二句を導入部、中四句を事柄の描写、最後の二句を結びの感懐に充てる形式をとっています。杜甫はこの形を好みました。
杜甫の特徴は題材の大きさにあり、場面の移り代わりが心の中に及んでいくことの見事さにあると思います。
四年間にわたる斉魯の旅が長くできたのは、袁州の父の官舎に滞在したからです。袁州は、遊ぶにはもってこいのところで、昔から「東文、西武、北岱、南湖」と呼ばれ,東に孔子ゆかりの「三孔」を仰ぎ,西に水滸伝ゆかりの「梁山泊」があり、北には「泰山」がそびえ、南には「微山湖」を望めます。また、「杜甫」ゆかりの地である少陵台もこの地にあります。北岱といわれるように袁州から北80kmに泰山があり、足を延したのです。「望嶽」は杜甫の残された作品の中では初期の名作とされています。また、みなぎる若さ満ち溢れる詩といえます。
望嶽(岱宗夫如何)
岱宗夫如何,齊魯青未了。造化鍾神秀,陰陽割昏曉。
盪胸生曾雲,決眥入歸鳥。會當凌絶頂,一覽衆山小。
泰山はどんな山か,斉魯にまたがり緑はどこまでもつづく
天地万物の理はすぐれた妙をあつめ,太陽と月が朝と夕べを分ける
胸を時めかせ曾雲が湧き,眥を決するなか鳥がねぐらに帰ってゆく
いつの日かきっと山頂をきわめ,群小の山を見おろすであろう
高大な山、泰山を望む。また、四方の群小の山々を見下ろす泰山のようになりたいと願う。
杜甫の後期の詩には見られない若さあふれるの詩風です。 この詩もはじめの二句を導入部、中四句を事柄の描写、最後の二句を結びの感懐に充てる形式をとっています。・高大な山、五岳の長である泰山からながめる。そうありたいと願う。つまり、四方の群小の山々を見下ろす泰山のようになりたいと願うのです。有り余る自分の才能を生かせば天下を見下ろせるようになると思っていたのです。
(741) 杜甫は開元二十九年のはじめに斉趙の旅から洛陽にもどり、河南府偃師(えんし)県の北郊、首陽山(しゅようざん)下の尸郷亭(しごうてい)に陸渾荘(りくこんそう)を営みました。陸渾荘を地名とする説もありますが、杜甫は家宅の名のように用いています。地名をもって家をいうことは現在でも行われていますので、いずれとも決め難いのですが、杜甫はその家を「尸郷の土室」と呼んで、窰洞(ヤオトン)でした。
杜甫は開元二十九年(741)29歳のはじめに斉趙の旅から洛陽にもどり、河南府偃師(えんし)県の北郊、首陽山(しゅようざん)下の尸郷亭(しごうてい)に陸渾荘(りくこんそう)を営みました。陸渾荘を地名とする説もありますが、杜甫は家宅の名のように用いています。地名をもって家をいうことは現在でも行われていますので、いずれとも決め難いのですが、杜甫はその家を「尸郷の土室」と呼んでいます。したがって、窰洞(ヤオトン)であったことは確実です。
家を構えたことから、杜甫はこの年に妻を迎えたとする説が有力です。しかし、子供の生年からすると、結婚はもう少し後のことと思われます。杜甫は30歳になっていますので、そのころ病気になっていたと思われる仁風里の「おば」の家に、いつまでも厄介になってはいられなかったのでしょう。
開元は二十九年で終わり、翌年は天宝と改元されますが、天宝元年に洛陽の「おば」が亡くなり、杜甫は墓誌銘を作って丁寧に葬ります。杜甫の毎日は「尸郷の土室」から洛陽に出かけていって知友と交わり、権貴の邸宅に招かれて詩を贈ったりすることです。こうした交際は官途へ近づくための方法として、当時の知識人の誰もがやっていたことです。
杜甫が洛陽の人士と交わっていた天宝の初年、李白は長安に召されて翰林供奉(かんりんぐぶ)になっていました。
天宝三載(744)32歳の春、李白は長安を辞して東に向かう途中、洛陽に立ち寄ります。都で著名の詩人が洛陽に来たというので、杜甫は李白を訪ねます。二人は文学について語り合ったと思われますが、杜甫は李白の強烈な個性に魅せられ、李白と共に旅をしたいと思います。しかし丁度そのとき、杜甫の祖母が亡くなりますので、秋になったら陳留(河南省開封市)で再会する約束をして別れました。
秋八月になって杜甫が李白のあとを追うと、李白はすでに宋州(河南省商丘市)に移っていました。杜甫は宋州で李白と再会し、そのころ近くを旅していた高適(こうせき)も加わって三詩人の梁宋(りょうそう)の旅がはじまります。それは同じ時期を回顧する二篇の詩が「壮遊」の詩と同じ大暦元年に作られているからです。「遣懐」はそのひとつで、「宋中」(宋州)で遊んだことを詠います。
宋中で出会った李白、高適(こうせき)、杜甫の三人は気が合って酒屋に繰り込み、文学を論じます。三人のなかでは杜甫が年少(33歳)ですので、李白と高適は若い才能を見出したと喜ぶのです。三人は宋州の「吹台」(孝王の旧苑)に登り、あたりの荒れた平原を見まわしながら、昔のことを思い出します。
詩中に出てくる「芒?」は芒山と?山のことで、漢の高祖劉邦が若いころ官憲の追求を逃れて身を隠したという伝説の場所です。「芒?」は宋州の東90kmのところにありますので、吹台からは見えませんが、ここで見ているのは「芒?」から立ち昇ったという劉邦の雲気(天子の生まれる気運)です。三人は劉邦の創業のさまを思って感慨にふけるのでした。しかし、漢の雲気もいまは消え去って、雁や家鴨が啼き交わすだけだと、王朝の衰退を歎きます。唐代の詩で唐を漢や秦に例えるのは通常の手法です。
宋城の東北には、当時、孟諸沢(もうしょたく)という沼沢が広がっていて、良い猟場でした。三人は秋の終わりから冬のはじめにかけて、孟諸沢で狩りの遊びをしました。
三人は狩りが終わると、孟諸沢の東北にあった単父(山東省単県)の東楼に登楼して、酒宴を開いたことが李白の詩でわかります。「単父台」というのは単父の北にあった琴台(きんだい)のことで、三人がここを訪ねたのは孟諸沢での狩りのあとでしょう。琴台はむかし孔子の弟子の?子賎(ひつしせん)が琴を奏しながら良い政事を行ったという伝説の場所です。
「昔遊」の詩句からは、杜甫が安禄山の乱が迫っているのを予感しているような印象を受けますが、それは「昔遊」が後年の作だからでしょう。安禄山は天宝元年に平盧節度使になったばかりで、三人は名前も知らなかったでしょう。杜甫も「是の時 倉廩実ち 洞達 寰区を開く」と詠っているように「開元の盛世」はなおつづいていたのです。
単父での交遊のあと、李白と杜甫は高適と別れ、二人は斉州(山東省済南市)へ行くことになりました。単父から斉州へゆく途中には、?州があります。?州はこのころ魯郡と改称されており、?州都督府の司馬であった杜閑もすでに転勤していたらしく、杜甫は父のもとに立ち寄らずに斉州に行っています。
斉州に着くと、李白は道士の資格を取るために、斉州の道観紫極宮の道士高如貴(こうじょき)のもとに入門します。杜甫は李白といっしょに斉州に来たものの、道士の修行にまで李白とつき合う気はありません。そこで当時、斉州司馬として斉州に赴任してきていた李之芳(りしほう)のもとに身を寄せます。李之芳は太宗の玄孫で皇室の一員ですが、なにかの事情で地方の司馬の職に就いていたようです。
杜甫は翌天宝四載(745)33歳の夏の終わりまで斉州にいて、李之芳の知人や斉州の知識人と交流して過ごします。秋になると斉州を出て魯郡の李白の家を訪ね、しばらく李白といっしょに暮らします。李白は道士の修行を終えると、魯郡の「魯の一婦人」と称される女性のもとで日を過ごしていました。魯郡では杜甫は李白に連れられて、道士や隠士のもとを訪れたりしますが、杜甫は道教や隠士の生活にあまり深入りはしませんでした。
官途にも就けずに魯郡のあたりをさまよっている自分自身を批難しているのです。天下国家のためにつくすのが自分たちの役割ではないかと反省している詩と思われます。
昨年の秋に梁宋の旅に出てから、すでに一年が経過しています。このころ杜甫の父杜閑は奉天県(陝西省乾県)の県令になっていたらしく、杜甫は父から長安に出てくるように促されていたと思います。やがて李白と杜甫は、魯郡曲阜の東北にある石門山の林中で別れの杯を酌み交わします。
杜甫は李白と別れて洛陽にもどると、その年の内か、翌年の正月には長安に出たと思われます。長安に出るとすぐ天宝五載(746)34歳のはじめに、杜甫は妻を迎えたと思われます。当時の士家の長子の結婚に親が関与しないはずはありませんので、父杜閑が縁組の手はずをととのえていて、杜甫はそれに従ったのでしょう。
杜甫はすでに三十五歳になっており、杜家の後嗣として、いつまでも詩的放浪の生活をつづけていることは許されなかったのです。杜甫の妻は司農少卿楊怡(ようい)の女(むすめ)で、司農は司農寺、つまり農業のことをつかさどる実務担当役所の少卿(従四品上:次官)の娘ですので、任官もしていない身分の杜甫としては高級官僚の娘をもらったことになります。妻の楊氏は、杜甫よりは十歳年少であったとみられていますので、結婚のとき二十五歳くらいになっていたことになります。当時の女性としては、相当の晩婚ということになります。
杜甫は結婚すると、長安にとどまって任官のための運動をはじめました。都のしかるべき人を頼って詩を献じ、機会があれば推薦してほしいと依頼して歩くのです。これは当時、一般に行われていた任官のための就職運動で、誰でもがやっていたことです。奉天県の県令であった父親の援助にたよる新婚生活であったと思われますが、杜甫はできるだけ交際の輪を広くして、求められれば貴公子たちの舟遊びの場にも出かけてゆきました。
杜甫が長安で就職活動をはじめた前年の天宝四載に、玄宗は愛妃の楊太真(ようたいしん)を貴妃(きひ)に任じていました。玄宗は皇后の死後、皇后を置いていませんでしたので、楊貴妃は後宮第一の人になったのです。その玄宗が制挙(せいきょ)を実施すると発表しました。
制挙は通常の貢挙とは別に天子が臨時に行う任用試験で、一芸に秀でた者を全国から長安に集め、考課するのです。楊貴妃は玄宗の息子(死んだ皇后の子)の妃であったものを奪って自分のものにしたので、儒教的には筋のよいものではありません。玄宗は広く人材を野に求めて、人気の回復を図るために制挙の実施を思いついたものと思われます。
杜甫にとっては願ってもない機会ですので、勇躍してこれに応募します。試験は天宝六載(747)の春に行われましたが、合格者はひとりもいませんでした。これには裏があり、当時、宰相であった李林甫(りりんぽ)は、天子が制挙によって新しい人材を登用するのを嫌っていました。李林甫は開元二十二年に宰相(複数制)に列して以来、知識人の文人宰相をつぎつぎに辞職に追い込み、権力を一手に掌握しようとしていました。そこで李林甫は、制挙の結果「野に遺賢なし」と奏上し、合格に値する者はひとりもいなかったと報告したのです。
杜甫は不合格の通知に失望しましたが、どうすることもできません。この年、妻の楊氏は長女を出産したと推定されます。杜甫は仕方なく再び詩才による任用に奔走します。しかし、事は一向に進まなくなりました。宰相の李林甫が人材の採用を望んでいないことを知って、政府の高官たちもあえて火中の栗を拾おうとしなくなったのです。
丁度そのとき、杜甫の姻戚の韋済(いさい)が尚書左丞(しょうしょさじょう)になって長安に赴任してきました。韋済の家は祖父・伯父・父と三代にわたって宰相を出したほどの名門で、前任は河南尹(河南府の長官)でしたので、杜甫は洛陽にいるときから目をかけてもらっていました。天宝七載(747)35歳、正月に「丈人」(おじ)韋済が長安に着任すると、杜甫はすぐに訪ねていって詩を献じました。
「李?」はそのころの文壇の長老で、杜甫は斉州司馬の李之芳のもとに滞在していたとき、北海太守(青州刺史)であった李?と面識を得て、交際をしていました。「王翰」は「涼州詞」(葡萄の美酒 夜光の杯…)の作者で、当時評判の詩人でした。その王翰が隣に住んで親交を結びたいと言っているというのです。
今回の十句は、都での就職活動の辛さです。「驢に騎ること三十載」というのは、詩人のわびしい暮らしの例えとして用いられる常套句です。親戚の「おじ」への甘えからか、飲み残しの酒や冷えた焼き肉を与えられ、みじめな屈辱的な生活をしていることを包み隠さずに言っています。
「主上に頃ろ徴され」というのは、制挙に応じたことをいうのでしょう。これに合格して一挙に政事の世界に躍り出ようとしたけれども、「青冥 却って翅を垂れ ??として鱗を縦ままにする無し」と、いまだに不自由な浪人ぐらしを強いられていると訴えます。
杜甫はあきらめて都を捨てようかと思うこともありますが、なお終南山(長安の南にあり、宮仕えというのに等しい)に未練もあり、渭水(長安の北を流れており、都というのに等しい)を振りかえらずにはいられないと訴えます。お力添えがあれば、きっとご恩に報いるつもりですとも懇願します。そして、ひとたび都を出てしまったら、自分は白?のような自由の身になって、二度と官途をめざすことはないでしょうと、脅迫めいたことまで口にします。
杜甫は必死でした。尚書左丞(正四品上)は尚書省六部を束ねる都省(としょう)の次官で、左丞は六部のうち吏部・戸部・礼部の担当ですので、韋済は官吏の任用を左右する権限の中枢に就いたことになります。杜甫が期待するのも当然です。杜甫は吉報があるものと信じて待っていましたが、年末になってもなんの音沙汰もありませんでした。おそらくは制挙を受けて不合格とされたことが、かえって障害になったのでしょう。
李林甫は制挙の結果を「野に遺賢なし」と奏上しています。だから詩文の才で任用を推薦するのは、李林甫の顔をつぶすことになるのです。李林甫はすでに政府高官の地位を自由に変えるだけの権力を握っていましたので、韋済も手の施しようがなかったと思われます。痺れを切らした杜甫は、天宝八載(749)になると妻子をともなって洛陽にもどってしまいました。
杜甫が妻子を連れて洛陽にもどったころ、玄宗は外征に力を入れるようになっていました。西方で吐蕃(チベット)が勢力を増し、唐の西域への交易路を侵すようになったからです。
安西副都護の高仙芝(こうせんし)は遠く西方に兵をすすめ、将軍董延光(とうえんこう)は吐蕃の石堡城(青海省湟源県付近)を攻めました。しかし、董延光の軍は吐蕃に敗れて敗走しましので、こんどは河西節度使の哥舒翰(かじょかん)が六万三千の大軍を率いて再度石堡城を攻め、多数の犠牲者を出して落とすことができました。
杜甫はそんななか、再度長安に出てきました。洛陽にいても、人々の目は西を向いていて、任官の機会からは遠ざかり、気分は滅入るばかりです。天宝九載(750)には長子宗文(幼名熊児)も生まれ、一家は四人になっていました。
長安に着くと、西征の兵馬の列が連日のように都門を出て西に向かっています。杜甫も人ごみにまじって、それを見にゆきました。「兵車行」(へいしゃこう)は杜甫の社会詩の最初の名作とされています。
唐代の兵制は、このころまでは農民からの徴兵が維持されていました。農家の正丁が兵役の義務を負っていたのです。杜甫がさらに問うと、四十歳を過ぎたその兵士は、十五歳のときから戦に駆り出され、いままた辺境の守備にゆくところだと言います
兵士は農作も満足にできないのに税金は厳しく取り立てられ、納める手立てもありませんと訴えます。そして「信に知る 男を生むは悪しく 反って是れ女を生むは好しきを」と有名な五言の二句を置きます。女の子なら近所に嫁にやれるが、男の子は戦場の土となって消えてしまうというのです。友人の高適(こうせき)は河西節度使哥舒翰の幕僚として吐蕃との戦争に参加していますので、杜甫は戦場の悲惨なようすをつぶさに耳にしたと思います。杜甫は戦場に行ったわけではありませんが、戦争の悲惨を人民の側から詩に取り上げ、名作として仕上げました。
「奉儒守官」を人生の目的とする杜甫は、任官の機会を得られないまま四十歳になっていました。天宝十載(751)38歳正月に、杜甫は延恩?(えんおんき)に「三大礼の賦」とそれに付した表(上書)を投じました。延恩?というのは、大明宮の東西南北、四つの門に設けられた投書箱で、一般の民が天子に意見を述べるものです。杜甫は直接天子に訴えて、自分を知ってもらおうと投書に頼ったのでした。
「三大礼の賦」は玄宗の政事を礼賛するものでしたので、天子の目にとまったらしく、杜甫はほどなくして集賢院待制(しゅうけんいんたいせい)に任じられました。集賢院は宮中の図書寮ですが、待制というのは御用掛り候補といった意味です。順番が来れば選考・登用の機会が与えられるという程度のものです。それでも、杜甫は期待しましたが、春が過ぎても夏が過ぎても呼び出しはありませんでした。杜甫は自分が当てにしている人の好意というものが、いかに当てにならないものであるかを、しみじみと知ることになります。
もちろん杜甫にも、心許せる友人はいます。しかし彼らも、杜甫と似たような境遇の詩人たちです。秋になって杜甫は、詩人の岑参(しんじん)、高適(こうせき)、儲光羲(ちょこうぎ)らと慈恩寺の塔に登りました。現在も大雁塔として残っている仏塔です。
詩ははじめの八句で天空にそびえ立つ慈恩寺塔の勇姿を描きます。その姿は人々を勇気づけるようなものではなく、さまざまな憂いを呼び起こします。「仰いで龍蛇の窟を穿ち」という表現は、甎(せん)を積み上げた大雁塔の螺旋階段を最上階まで登ってみれば、いまもそのままであることが実感できるでしょう。
そのころ安西都護の高仙芝(こうせんし)は、怛羅斯(タラス:キルギス共和国シヤンブィル)河畔で黒衣大食(こくいタージー:イスラム帝国アッバース朝)の大軍と対峙していましたが、敗れて退き、怛羅斯城に立てこもって防戦していました。しかし、葛羅禄(カルルク:トルコ族の一派)の内応に遇って大敗します。史上有名な「タラスの戦い」です。
同じころ剣南節度使の楊国忠(ようこくちゅう)は雲南の南詔(雲南省大理一帯)を攻めていました。天宝十載(752)40歳、楊国忠はみずから兵を率いて南詔を再征しようとしていましたが、都から急使が来て長安に呼びもどされます。楊国忠が長安に着いた直後の十一月に宰相李林甫(りりんぽ)が病死して、楊国忠は後任の宰相に任じられました。李林甫は十八年間も権力の座にあり、楊貴妃の一族といえども李林甫の顔色をうかがいながら用心していました。いまや楊貴妃の「ふたいとこ」にあたる楊国忠が宰相になり、楊氏一族には恐れるものがなくなりました。
杜甫は集賢院待制のまま呼び出しが来るのを待っていましたが、とうとう待ちきれなくなって、天宝十二載(753)41歳の正月に再び賦を書いて延恩?(えんおんき)に投じました。そのころ楊貴妃の一族は、わが世の春を謳歌していました。貴妃の兄や姉三人は高位に任ぜられ、宮中にも自由に出入りできる身分です。季春の三月三日は二十四節気には当たりませんが、厄除けの日として水辺で身を清める風習がありました。清明節も近いので恵風の吹く気持ちの良い季節です。そのころになると、長安の遊楽の地、曲江のほとりでは、宴遊の人々で賑わいを程します。杜甫も出かけて行ったようです。 いましも曲江の水辺には、宴会のための大きな天幕が張られ、なかでも豪華なのは楊家の三夫人の天幕です。杜甫は中に入ったわけではないと思いますが、天幕のなかの卓には贅沢を極めた料理が並べられていると対句で詠います。駱駝の瘤を煮たものや、新鮮な魚の料理です。楊貴妃の姉、三夫人の天幕のあたりには、権力者に取り入ろうとする人々でごった返しており、後から来た人もためらいがちに馬を降りて天幕のなかに入ってゆきます。
頽廃は雪のように降りつもって、青い鳥が赤い絹の領巾を口にくわえて飛び去る姿が象徴的に描かれています。結びの二句は杜甫の感想で、「手を炙れば熱す可し 勢いは絶倫なり 慎んで近づき前む莫れ 丞相嗔らん」と右丞相楊国忠の横暴と危険を指摘するのです。
杜甫が何将軍の山荘をはじめて訪れた天宝十二載(753)41歳に、長安は日照りと水害に交互に見舞われました。そんななか、杜甫が妻子をかかえて浪人暮らしをつづけられたのは、奉天県令の父杜閑の援助があったからだと思われます。
父杜閑の官歴は奉天県令までで、死去の年はわかっていません。しかし、天宝十二載のころまでに死去していたとみられます。父親の死後に継室の盧氏と三子一女の異母弟妹が残されました。すぐ下の別の異母弟は、斉州(山東省済南市)管下の県の下級事務官になっていて、はやくに自立していました。
盧氏の生んだ長子杜観は杜甫が長安に出てきた年に生まれていますので、まだ八歳に過ぎません。ほかに杜占、杜豊の幼い弟と一女がいて、これら父の遺族五人の生活は杜家の嫡子である杜甫の肩にかかってきます。加えて、この年の秋には杜甫の次子宗武(幼名は驥子)が生まれていますので、杜甫は大家族をかかえて生活困窮の度が加わります。
任官して収入を得ることは、もはや一刻の猶予もできない状態になってきて、天宝十三載(754)の正月、杜甫は三度目の延恩?投書を行いました。そのほか中書省の起居舎人(従六品上)の田澄(でんとう)や宰相の韋見素(いけんそ)にも嘆願の詩を贈っています。
その春、杜甫は長安南郊の少陵原の一角、杜曲の地に家を借り、城内から転居しました。杜陵は杜甫の尊敬する遠祖杜預(どよ)の居宅のあった地ですが、転居の本音は自分も入れて十人の大家族になり、城内では暮らすことが困難になって田舎に移ったのでしょう。
杜曲に転居して間もない晩春のころに、杜甫は何将軍に書簡を書いたようです。住所の移転などを伝えたのかもしれません。すると何将軍から遊びに来ないかという返事が届き、杜甫は大喜びで出かけてゆきます。
延恩?に三度も賦と表(上書)を投じたけれども、宮中からは何の音沙汰もありません。杜甫は微禄でもいいから何とか禄にありついて、故郷の鞏県か陸渾荘にもどって土に親しむ生活をするのもいいと思ったりします。しかし、それも出来そうにない夢であることも分かっていて、茫然と酒杯を見つめているのです。
杜甫42歳、天宝十三載(754)のことですが、秋になると六十日間も雨が降りつづきました。前年も日照りと水害が交互に関中を見舞い、都は食糧不足に陥っていました。加えて今年の長雨です。城内では米の値段が高騰し、米一斗と夜具を取り換えるほどです。
大家族をかかえ、禄もない杜甫は生活に困窮し、妻子を奉先県(陝西省蒲城県)の妻の縁者に預けて急場をしのぐことにしました。妻の縁者が奉先県の県令をしていたのです。ところで困ったのは、父の遺族の盧氏一家をどうするかという問題でした。若い継母や異母兄弟まで妻の縁者に預けるわけにはゆきませんので、杜甫は盧氏の一家を尸郷亭の自分の家に移すことにしたのではないかと思います。これは諸書に未見で、私独自の推定です。
このとき盧氏の長子杜観は九歳になっていましたので、杜甫はこの弟は杜曲に残し、留守番などの手伝いをさせようと思いましたが、つぎの弟の杜占(七歳くらい)も兄といっしょに杜曲に残ると言い出しました。そこで、盧氏と末の弟杜豊と一女だけを首陽山下の土室に移すことにしたのではないかと思われます。以上の推定は今後の家族との関係から独自に推定したもので、文献の根拠はありません。
一家は驪山の麓で北と東にわかれ、このときに別れた盧氏と杜豊、妹とは再び会うことがありませんでした。杜甫は末の異母弟杜豊のことを生涯気にかけていましたが、とうとう会えないまま杜甫は亡くなっています。妻子を連れて奉先県に行った杜甫は、そのころ妻のお腹に子が宿っていましたので、その子(女児)の誕生を見届けてから冬のはじめに杜曲の家にもどってきました。
騒々しかった杜曲の家は、異母弟の杜観・杜占との三人暮らしになりました。しかし、杜甫には仕事がありません。「従孫」というのは当主の孫の世代に属する同族のことですが、従孫の杜済(とせい)という者が近くに住んでいましたので、夜明けに驢馬に乗って訪ねてゆきました。
杜済は杜甫よりも八歳しか年少でなかったようですが、のちに東川節度使兼京兆尹(京兆尹は寄禄官)に出世します。しかし、このころは官に就いていなかったようで、杜甫は「宅舎は荒村の如し」と言っています。「堂」というのは住宅の主室のことですが、堂前堂後は荒れた冬景色で、貧しいようすがうかがえます。 杜甫が来たというので、家人は急いで食事の支度をはじめたようです。杜甫は家事に託して事柄の本源を大切にしなければならないことを説きます。説きながら、自分は「嬾惰なること久しく」、お前たちの働く様子を見ていると走っているようだと、ほめるのも忘れません。
杜甫はどうにか天宝十三載の冬を乗り切り、天宝十四載(755)の春を迎えました。官への働きかけの効果もないままに夏が過ぎ、秋になると杜甫は奉先県の妻子を訪ねます。女児が無事に育っているのを眺め、それから奉先県の北45kmのところにある白水県まで足をのばします。
白水県には母方の「おじ」崔明府と崔少府がいます。明府は県令、少府は県尉のことですので、親族が同じ県の長と次長をしていたことになります。杜甫は「おじ」たちの家にしばらく滞在したあと、帰途に奉先県に立ち寄って秋の終わりに長安にもどってきました。
するとそれを待っていたように、十月のはじめに「河西の尉」という赴任地が示されてきました。河西の尉については不明な点もありますが、河西節度判官の尉という解釈があります。当時、涼州(甘粛省武威県)にあった河西節度使の節度判官の尉(副官)の地位はどうかと内示してきたのです。
杜甫は河西が僻遠の地であることを理由に辞退します。はじめに内示される任地は、断られることを前提とした空位の慣行があったとも言われていますので、杜甫は改めて右衛率府兵曹参軍事(うえそつふへいそうさんぐんじ)に任命されました。これは東宮(皇太子)に属する諸率府の事務官(従八品下)で、太子禁衛軍の兵員の管理をする事務職です。 微職ですが杜甫はこれを受けます。 やっと任官が決まって生活安定の見込みが立ったので、杜甫は奉先県に預けてある家族を迎えに行くことにしました。この旅で作った詩は五言百句、一韻到底(いちいんとうてい)の迫力ある大作です。全部を掲げるために十回に分けて掲載します。
天宝十四載(755)冬十一月のはじめ、杜甫は馬車で真夜中に長安を発ち、奉先県への路を急ぎます。冷たい風が北の砂漠地帯から吹きつけてくるなか、杜甫は四十四歳も過ぎようとする冬になって、やっと官職にありつけた自分の人生をかえりみます。
奉先県へ行くには、驪山の麓で左折して北へ向かわなければなりません。やがて涇水が渭水に合流する地点の少し下流いたり、そこで渭水を渡るのです。流氷が西から流れてきますが、それは涇水の上流の??山から流れてきたものであろうと杜甫は想像します。官人である杜甫は渡橋用の別の車に乗り換えますが、一般の人は揺れる浮梁(小舟を横につなぎ合わせて板を敷き並べた舟橋)を手を取り合って渡ってゆきます。 奉先県に着いて妻子のいる家の門にはいると、杜甫は思いがけないことに出会います。門内から泣き叫ぶ声が聞こえてきて、幼いわが子が飢えて死んだところでした。杜甫は嘆き悲しみますが、それと同時に人の子の親として、食べ物がなくてわが子を死なせたことを恥じるのでした。杜甫の詩の特徴のひとつは、自分のことを詠うだけでなく、わが身を通じて人のことを思いやる心が著しいことです。唐代では士身分の者は租税や兵役などの役務(えきむ)から免除されていました。杜甫は士身分ですので、官に就いていなくても諸役を負担する必要はありません。
そんな身分の自分でさえ、生活が苦しくて幼い子供を死なせるほどであるのに、一般の人はどんなに苦しんでいるだろうと、失業している人や遠征にかり出されている人々の苦労を思いやるのです。憂いは山のように拡がるけれども、微役の身ではどうすることもできないと嘆きます。
杜甫が奉先県の家族のもとに着いたころ、東北の幽州(北京)で重大な事件が発生していました。十一月九日の早朝、節度使の安禄山(あんろくさん)が兵を挙げたのです。
李林甫が宰相であったころ、安禄山と楊国忠は互いに天子の寵を競い合う競争相手でした。ところが李林甫が死んで楊国忠が宰相になると、楊国忠は安禄山を危険な人物として排除しようとしました。身の危険を感じた安禄山は「君側の奸を討つ」と称して立ち上がったのです。安禄山にははじめ国を奪うといった野心はなかったものと思われます。
奉先県で幼児の死を悲しんでいた杜甫は、叛乱発生の報せを聞くと、家族を長安に連れて帰るのは中止して、すぐさま都にもどります。なったばかりとはいえ、杜甫は右衛率府兵曹参軍事ですので、急いで任務に就く必要があったのです。その間に安禄山の軍は破竹の勢いで河北の平原を南下し、十二月三日には黄河を渡ります。十三日には洛陽になだれこんで、東都を占領してしました。朝廷は河西・隴右節度使の哥舒翰(かじょかん)を兵馬副元帥に任じて潼関の守りを固めます。
明けて天宝十五載(756)42歳の正月三日、安禄山は洛陽で即位して皇帝を称し、国号を大燕、年号を聖武と定めました。政府軍があまりにももろく退いたので勝利に気を良くし、また兵の士気を高めるためにも建国の志を示す必要があったものと思われます。そのころ政府軍の側では河東の太原に兵を出し反撃に転じ、河北でも勇気のある郡太守らが兵を集めて、安禄山軍の背後を撹乱し、抵抗をはじめていました。
潼関の哥舒翰はこれらの動きを見ながら反撃の機会をうかがっていましたが、長安の楊国忠は一刻もはやく洛陽の賊を退けるように督促します。哥舒翰は通敵の疑いすらかけられたので、六月八日に潼関を出て、桃林(河南省霊宝県の西)で安禄山軍と戦いますが、大敗してしまいます。
杜甫は潼関の戦線が緊張してきたのをみて、六月のはじめに奉先県に行き、家族を白水県の母方の「おじ」崔氏のところに移していました。そこに唐軍潼関に敗れるとの敗報が伝わってきましたので、杜甫は一家を連れてさらに北へ向かって避難します。五言古詩「彭衙行」(ほうがこう)は、このとき白水県から友人孫宰(そんさい)のいる同家窪(どうかわ)までの逃避行を詠うものです。彭衙は白水と同家窪の途中にある町で、白水県に属しています。距離はさほどではありませんが、幼児らを連れて夜の山道を徒歩でゆく逃避行は困難を極めたようです。
夜道で虎や狼の吠える声が聞こえ、幼い娘は恐がって泣き叫びます。食糧の用意もなかったので、苦いすももを拾って食べる子もいます。このあたり六句の描写は目に見えるようで、杜甫の作詩力のすごさを感じます。
時期は陰暦六月の中旬、潼関陥落の直後のことで、夏の雷雨が五日もつづきます。雨の中、雨具の用意もないので濡れてふるえながら、泥水の山道をころびつつ助け合って避難してゆくようすが描かれます。杜甫の一行は妻と幼い二子二女のほか、異母弟の杜観と杜占も伴っていたはずで、杜甫を入れて八人です。荷物を持つ従者も二人くらいは従えていたかもしれません。
杜甫一家の逃避行はつづきます。野生の果実で飢えをしのぎ、野宿をする旅です。このとき杜甫は同家窪の孫宰の家でしばらく体を休め、さらに北の蘆子関に抜けようと考えていたようです。蘆子関は漢代の長城に接する関門の町で、北にはオルドスの砂漠地帯が広がっています。杜甫は最北端の地まで家族を逃がすつもりであったようです。潼関の敗戦の衝撃がいかに強かったかがうかがわれます。
同家窪の孫宰の家に着いたのは暗くなるころでしたが、孫宰は灯火をともし扉を開いて迎え入れてくれました。「紙を剪って我が魂を招く」のは遠来の客を迎え入れるときの招魂の儀式でしょう。孫宰は在地の知識人と思われ、杜甫を尊敬していて鄭重に迎えます。それから連れている家族を引き合わせたりしますが、このあたりの描写はとても細やかで、杜甫の繊細な感情があふれるように詠われているのを感じます。
杜甫は同家窪からさらに北へ65kmほど行った?州(ふしゅう)に辿りつき、?州(陝西省富県)の三川県羌村(きょうそん)というところに家を見つけて、そこにとどまることにしました。蘆子関までは行かずに途中でとどまったのです。
『月夜』 杜甫が家族を?州羌村に避難させている間に、都では大変なことが起こっていました。六月十三日の早朝、玄宗は楊貴妃や一部の皇族、側近をつれて長安を脱出したのです。護衛として龍武将軍陳玄礼(ちんげんれい)が禁衛軍を率いて従いました。
玄宗は翌十四日に長安の西40kmほどの馬嵬駅(陝西省興平県)につきますが、そこで禁衛の兵が不満を爆発させ、宰相の楊国忠と楊氏の一族を殺害しました。兵たちはさらに楊貴妃の処刑を要求して一歩も進もうとしません。玄宗は拒みきれなくなって楊貴妃をそばの仏堂で縊り殺させます。
玄宗は皇太子李亨(りきょう)に都の防衛を命じて、みずからは蜀の成都へ向かいます。しかし、長安は十日ほどで安禄山軍に占領されてしまいますので、李亨は兵をととのえるためにひとまず霊州(寧夏回族自治区霊武県)に向かいました。霊州には朔方節度使の使府が置かれていて、軍事上の拠点であったからです。
皇太子は七月十三日に霊州で伝国璽のないまま即位をして帝位に就きます。同時に年号も至徳と改元しました。こうした都の動きは羌村の杜甫にも伝わってきます。杜甫は七月の末になって霊州の新帝粛宗(しゅくそう)のもとに駆け付けるため、家族を羌村に残して北へ馬を走らせます。?州から霊州までは西北に350kmほどありますが、蘆子関(陝西省靖辺県)の近くまで来たところで安禄山軍に捕らえられてしまいました。杜甫を捕らえたのは大同(山西省大同市)の高秀岩(こうしゅうがん)の兵でしょう。安禄山は幽州で兵を興すと同時に大同の軍を朔方郡(夏州以北のオルドス地方)に派遣して、北から関中に攻め込ませていました。
安禄山軍に捕らえられた杜甫は、長安に連行されます。長安では多くの政府高官が賊軍に捕らえられていて、洛陽の政府に協力を強要されていましたが、杜甫は微官であったので安禄山の政府に仕えることは命ぜられず、軟禁処分になって城内にとどまることを命ぜられます。
五言律詩「月夜」は長安に連行されて間もない晩秋の作で、?州羌村に残してきた家族を想う詩です。この詩は名作として有名ですが、不思議なのは杜甫が自分の妻を宮女かなにかのように優雅に描いていることです。これは杜甫の時代までは家族や特に妻のことを詩に詠う伝統がなかったからだと思います。唐代の詩の多くは女性といえば宮女や妓女の閨怨を詠うものです。天才詩人の杜甫も、このときまでは自分の妻をどのように詩に詠っていいのか分からなかったのだろうと思います。
『悲陳陶』 杜甫が長安に軟禁されていた至徳元年(756)45歳の八月ごろ、霊州の粛宗は事後承認のかたちで成都の玄宗を上皇天帝にまつりあげ、自分への譲位を求めます。その要請が成都に届くと玄宗はやむなく承認し、譲位の詔勅を起草して宰相の房?(ぼうかん)を使者として粛宗のもとに届けさせました。
その間、粛宗は朔方郡に出陣していた朔方節度使郭子儀(かくしぎ)の軍を霊武に呼びもどし、霊州を出て東南に軍を進め、九月には順化(甘粛省慶陽県)に進出していました。房?が粛宗のもとに着いたのは順化においてでした。粛宗は玄宗が上皇天帝になることを受け入れ、譲位の詔勅を送ってきたことを喜び、房?をとどめて自分の政府の宰相に任じました。
粛宗の軍は南下して十月には彭原(甘粛省寧県)に到り、房?に首都の奪還を命じます。房?は十郡の兵六万余を率いて南下し、西から長安に迫ります。安禄山の軍との戦闘は十月二十一日に咸陽(長安の西北)の西の陳陶斜で行われ、政府軍は一日の戦闘で大敗してしまいました。
杜甫は長安にあって政府軍の勝利を期待していましたが、敗れたのを知って詩を作りました。戦場のようすは想像でしょうが、長安に凱旋してきた安禄山軍のようすは実際に見たものでしょう。
『悲青坂』 陳陶斜の敗戦は彼我の戦闘方法に違いがあったからだと思われます。幽州の兵はこれまで北の胡賊と戦い、胡の降兵を自軍に取り込んでいますので、騎兵を中心とした突撃力の高い兵でした。それに対して房?は伝統的な兵法を重んずる指揮官で、兵車を並べ歩兵で進撃しようとします。賊将の安守忠(あんしゅちゅう)は風上から草に火を放って視界をさえぎり、官軍の混乱に乗じて騎馬で突撃してきたといいます。
敗れた房?は敗兵を太白山(陝西省武功県)の麓に集めると、兵をととのえて二日後の十一月二十三日に青坂に陣を構えます。詩中の「東門」を咸陽の東門と解する説もありますが、官軍は西から攻めていますので、東向きに門に対して布陣したと解しました。「黄頭の奚児」というのは黄色の狐の皮のかぶり物で頭を包んだ胡族の兵で、門を出て西へ前進してきました。たまりかねた味方の兵数騎が胡兵の挑発に乗って突出し、またも大敗を喫してしまいます。
杜甫はここは忍耐して明年を待てと言ってやりたいがどうすることもできないと、官軍の二度もの敗戦に心を痛めます。
『対雪』 この詩は陳陶斜・青坂の敗戦後ほどなく書かれたものと思われます。中四句を前後からはさむ形式の五言律詩で、はじめの二句で戦場の死者を悼み、自分は詩を吟ずるくらいしかできない老翁であると自分の無力を嘆きます。
中の四句は杜甫が坐している堂房から見える外の景色と室内のようすを描いていますが、わびしい無力感が色濃くただよっています。最後の二句で幾つかの州が賊の手に落ちたことをいい、「愁え坐して 正に空に書す」と言っていますが、これには故事があります。
晋末に殷浩(いんこう)という人が時の政事を愁えて、毎日空中に「咄咄怪事」の四文字を書いていたそうです。その意味は「ちくしょう おかしなことだ」といったつぶやきで、杜甫も同じような憤懣の文字を虚空に書きつけていると言っているのです。
『春望』 戦局は官軍不利のまま冬が過ぎ、明けて至徳二年(757)45歳の春になります。囚われの身にも春はかわりなくやってきますが、杜甫は城内にあって亡国の悲哀に沈んでいます。
五言律詩「春望」(しゅんぼう)は杜甫の詩のなかで、もっともよく知られた名作です。日本人の知っている漢詩の第一位が、この詩という統計もあるそうです。詩中の「簪」は冠(かんむり)をとめるピンのことで、冠は成人男子であることを示す被り物です。「渾て簪に勝えざらんと欲す」は心配で髪が薄くなり、冠も留めて置けなくなったと解されますが、裏の気持ちとしては、こんな国難の時に囚われの身では、冠をつけて人前に出ることもできなくなったという自責の念も含まれていると思われます。
『遣興』 杜甫は国のゆくすえを心配すると同時に、羌村に残したまま音信不通になっている家族のことも気になります。詩題の「遣興」というのは湧き出る思いを吐き出すという意味で、即興的な詩ですが感情がこもっています。
「驥子」というのは次男宗武の幼名で、このとき五歳でした。五歳で父親の詩を暗誦したりして賢いところのある次男に杜甫は注目しており、言葉を覚え始めるくらいの幼さで戦乱の世に遭遇した幼児に同情を寄せています。そして占領下、囚われの身では家族に便りを出すこともできないと嘆くのです。
『哀江頭』 杜甫は長安に軟禁されているといっても、城内での行動はかなり自由であったようです。春も盛りのころ、杜甫は曲江に行ってみます。「潜行す」と言っているので隠れて行ったのでしょう。曲江の数ある宮殿は門を閉ざしていますが、しだれ柳やかわ柳はいつものように新芽を出していました。
杜甫は江頭に佇みながら、玄宗と楊貴妃の遊宴の華やかであったころを回想します。楊貴妃の事件は起きたばかりですので、同時代に生きた杜甫が事件をどのように見ていたかがわかる貴重な作品です。 杜甫の居所は城内の南にあったらしく、家に帰ろうとするが、目は城北のほうをさまよったと詠っています。現実の杜甫の迷える姿が目に見えるような結びです。
城北は宮殿のある北であり、さらに城外の北には官軍がいます。宮殿には賊軍がたむろしていたでしょうし、城外の官軍には首都奪回の期待を寄せていたでしょう。目はその両方をさまようのです。なお、長安城内の南部は盛唐の時代でも家は少なく、農地や高官の別荘が点在していたようです。
40歳頃(742)からの杜甫は、社会的題材をとりあけて民衆に代わってうたうという社会詩人として名声をあげていった。
44歳のときに、知人の推薦によって右衛率府冑曹参軍事(皇太子の御殿を防衛する軍隊の兵器庫の管理者)に任官した。
任官後間もない45歳の時
安禄山の乱がおこり、杜甫は前年食糧疎開をさせていた家族の住まいを移すために疎開先に行ったが、そこで粛宗(しゅくそう)が霊武で即位(757年)したというニュースを聞いて、単身粛宗の行在所(あんざいしょ)に馳せ参じようとして行く途中で、安禄山側に捕らえられて捕虜にされ、長安の捕虜収容所に送りこまれてしまった。
【有名な「春望」の詩は、757年長安の捕虜時代、作者46歳長安での作】
翌年4月
収容所を脱走して、そのときは鳳翔(陝西省)に行在所を移していた粛宗のもとにたどりつき、格別の抜擢で左拾遺という天子側近の諫官にあてられた。
しかし、元来、科挙にも合格していなかった杜甫であったため、社会の秩序が少しづつ回復するとともに、華州司功参軍事という地方官に出されてしまった。47歳(758年)の6月のことである。
この時期の杜甫は、後世の人から「詩史」(詩による現代詩)と称されるほど、安禄山の乱を題材にして、たくさんの詩をうたいつづけた。
48歳の秋
華州司功参軍事として任官中は、杜甫の社会詩の最大傑作とされる「三吏三別」の6作品を作ったが、そのなかで政府のやり方を批判する発言があるということで、華州司功参軍事の官を免ぜられてしまった。
そののち、杜甫は、職を捨て妻子を連れて、放浪の詩人としての長期の旅に出る。
秦州から同谷をへて、48歳の12月に成都(四川省)にたどりつき、翌49歳のとき、成都の浣花渓(かんかけい)のほとりに草堂をつくり、54歳まで成都に滞在することになる。
この時期が、杜甫にとって最も恵まれた時期
かつての友人の巌武(げんぶ)や、高適(こうせき)が交替に、この地域の高官として着任し、杜甫の生活を見てやったりもした。
53歳のとき
剣南東川節度使の巌武の推挙により節度参謀・工部員外郎となったが、それも永くはつづかず、
翌年54歳の正月には官を辞して浣花草堂(かんかそうどう)にもどった。
そしてこの年の正月に高適が、4月には巌武が相ついで亡くなるとともに、杜甫は成都の生活に見きりをつけて、家族ともども再び旅に出た。
こんどの旅は、長江を利用しての水上の旅であったが、健康をむしばまれつつあった杜甫は、しばしば水上から陸地に上陸して、病気療養にあたらざるをえなかった。
55歳の秋から57歳の正月まで
?州(四川省)時代に、『秋興』八首の連作をはじめとして、詠懷古跡(羣山萬壑赴荊門)可惜(花飛有底急)
客至(舍南舍北皆春水)、瞿塘両崖(三峡傳何處)、?州歌十絶句(?東?西一萬家) 、復愁(萬國尚戎馬)
数々の名作を残した。
杜甫の芸術が最も結実したのは、この足かけ3年の?州時代であった。
57歳の正月 768年
?州を離れ、また長江を下って洞庭湖に向かい、さらに南下して長沙(湖南省)に向かおうとしたが途中で洪水にあい、あきらめて北上する途中、潭州と岳州(ともに湖南省)のあいだの水上で、家族に見とられつつ59歳の寿命を終えたのであった。
杜甫は江陵から北へ、都長安もしくは東都洛陽をめざすこともできたはずです。しかし、杜甫には帰郷に必要な資金もなかったでしょう。尾羽うち枯らして帰るわけにはゆかないのです。
おりしもそのころ、北の商州(陝西省商県)では兵馬使劉洽(りゅうこう)が防禦使殷仲卿(いんちゅうけい)を殺して叛乱を起こしていました。北への道は兵乱で塞がれており、帰郷の条件はととのっていませんでした。杜甫は長江を東へ下ります。
「江漢」この詩は大暦四年(769)の秋、潭州(湖南省長沙市)で作られたとする説もありますが、題名の「江漢」からすると、大暦三年(768)の秋、長江を下っている途中の作とするのが妥当のようです。頚聯の「落日 心は猶お壮んに 秋風 病は蘇えらんと欲す」の句も、未知の地に向かう杜甫が自分自身を励ましている句と考えられます。
これからの行く手についての考えを述べています。いろいろな故事を用いて行く先を修飾していますが、本当はあてのない旅であったので、飾る必要があったのでしょう。
「舟出江陵南浦 奉寄鄭少尹審」
「衡陽」(湖南省衡陽県)は洞庭湖の南にあり、雁はここまで渡南して北へ引き返すと信じられていました。「南征 懸榻を問わむ」の句は故事を踏まえており、?陽湖の南の洪州(江西省南昌市)に行くことです。
「泊岳陽城下」
長江を下る途中、杜甫は公安(湖北省公安県)に上陸して、県尉の顔(がん)氏と長安時代の友人で書家の顧戒奢(こかいしゃ)の世話になりました。しかし、ほどなく顧戒奢は江西に赴任することになり、杜甫は公安に二か月あまり滞在して、冬も深まった年末に岳州(湖南省岳陽市)に着きました。
この詩をみると、杜甫はとても元気なようです。詩文は湧くように生まれてくる。困難に遭っても意気はますます盛んであると詠っています。
杜甫は最終的には故郷の洛陽に帰る気持ちがあったと思われます。しかし、詩では「図南 未だ料る可からず」と南下の意思を示しています。岳陽は北と南の分岐点で、洛陽に行くには長江をさらに180kmほど東北に下って漢陽(湖北省武漢市)から漢水にはいって遡行しなければなりません。ところが杜甫は、世の中には何があるかわからないと、『荘子』の説話を引いて南に向かおうとしているのです。
「登岳陽楼」
岳州の渡津に舟をつけると、杜甫はすぐに岳陽楼に上ったようです。岳陽城は洞庭湖の湖口東岸にあって、岳陽楼は城壁の西門上に聳える三層楼でした。西南の眼下に洞庭湖を見渡すことができます。
「宿白沙駅」
杜甫の一家は岳陽で年を越し、翌大暦四年(769)の正月、洞庭湖を南へ下って潭州(湖南省長沙市)に向かいました。北の故郷ではなく、南の瀟湘の地へ向かった理由については、いろいろな説がありますが、乱後の北へ帰っても生活できないというのが隠された理由だったのではないでしょうか。
当時の洞庭湖は現在の六倍もの広さがあり、湖の南岸は現在よりも50kmほど南へ拡がっていたとみられています。洞庭湖の東南隅に青草湖と称する一角があり、白沙駅という宿駅がありました。杜甫は日暮れになって白沙駅の渡津に舟をつなぎました。
「清明 二首 其の一」
白沙駅を出ると、舟はすぐに湘水に入ります。潭州(湖南省長沙市)は湘水の河口に近い城市といってよく、陰暦三月のはじめ、清明節のころには潭州に着いていました。
清明節は同時に寒食明けでもあり、新しく火を起こして食事をつくり、墓参りや野遊びをします。陽暦では四月五日か六日にあたりますので、気候のよい季節です。子供が竹馬に乗るのも踏青(野遊び)の一種ですが、杜甫は故郷にいませんので墓参りはできません。土地に住む異族の子供の民族衣装や楚女の細い腰が杜甫の目にとまります。
「清明 二首 其の二」
清明節になったが、杜甫は金銭に窮し、貧しい食事しかできないといい、富貴も隠棲も人の考え方次第だが、自分は濁り酒に粗末な飯でがまんをしていると強がりを言っているのか、嘆いているのか、判断に迷うような詠いぶりです
清明節の日の詩というのに、其の二の詩はあまりにも悲痛で家族にも見せられなかったであろうと思われます。「右臂は偏枯し 半耳は聾す」と杜甫は体の不調を記録しています。そして、岸に繋いだ舟のなかで涙を流すのです。「悠悠たる伏枕 左書空し」は『詩経』関雎(かんしょ)の詩を踏まえており、輾転反側して悩み夜も眠れないほどであり、字も上手に書けないという意味でしょう。
蜀に流亡してからすでに十年がたち、洞庭湖の湖畔にあって季節は変わりなく移っていきます。長安の都も蜀の山河も、いまは遠いものになってしまいました。杜甫はそうしたことを思いながら、浮き草の花の白さに打ちのめされると、漂泊の人生を嘆くのです。人々が楽しむ清明節は、哀しみの言葉でむすばれます。
「清明二首」のうち其の二の詩は、杜甫の苦悩が生々しく描かれ、佳作といえるでしょう。
「朱鳳行」
杜甫の当面の目的地は、潭州から湘水をさらに150kmほど南へ遡った衡州(湖南省衡陽市)でした。知己の韋之晋(いししん)が衡州刺史をしていたので、それに頼るつもりであったようです。その途中の湘水西岸に高さ1290mの南岳衡山があり、南北400kmにわたる連山となって横たわっていました。
詩題の「朱鳳」は衡山に棲むという朱色の鳳凰のことで、南は赤、神獣は朱雀(すじゃく)であることにちなんだ伝説の鳥です。杜甫は三句目以下で、自分を「朱鳳」に例えています。
「閣臥病走筆寄呈 崔・盧両侍御」 769年 58歳 夏~秋
杜甫が潭州に着いたときは、頼りにしていた韋之晋が四月に急死したあとでした。不運としか言いようがありません。頼る者をなくした杜甫は、それから翌年の大暦五年(770)四月まで、舟中や江辺の楼を宿所としながら、市場で薬草を売ったり、州府の知己の好意にすがったりしながら糊口をしのいでいたようです。
この一年にわたる潭州滞在は北へもどるのに充分な時間の余裕であると思われますが、杜甫はなぜかあてもなく潭州にとどまっています。病気のせいもあったかもしれませんが、帰るに帰れない経済的な窮状におちいっていたと見るべきでしょう。.
詩は58歳、夏の終わりか秋のはじめに、崔渙(さいかん)と盧十四(ろじゅうし:十四は排行)に食べ物と酒をねだったものです。崔氏と盧氏は旧知の元侍御で、このとき潭州に左遷されて来ていたものと思われます。この詩は杜甫一家が食事にも事欠くような窮状におちいっていたことを示しています。
「小寒食船中作」
困難な生活のうちに一年が過ぎ、杜甫は五十九歳の春を迎えました。その春、舅父(きゅうふ:母方のおじ)の崔偉(さいい)が?州(ちんしゅう:湖南省?州市)の録事参軍(刺史代理)になって赴任する途中、潭州を通過しました。杜甫は久しぶりに親族の「おじ」と会い、四方山話をした。上流の任地へ赴く「おじ」を見送ってから、杜甫は潭州で迎える二度目の寒食節を過ごします。詩題の「小寒食」は寒食節の三日目、最後の寒食日のことです。
「清 明」
小寒食の翌日は清明節です。大暦五年(770)の清明節は旧暦三月三日で、上巳節と重なっていました。後半で出てきますが、このことによって杜甫はこの時まで潭州にいたことの証明になります。
清明節の日には野外で遊ぶ習わしであり、人出があります。杜甫も人ごみに混じって郊外に出かけたようです。潭州の湘水西岸には岳麓山があり、山中には岳麓寺と道林寺の二寺がありました。寺の境内は遊宴に適しており、潭州駐屯の武将たちが宴会をひらいていました。夕刻になったので、杜甫は山を下りて帰途につきます。
「江南逢李亀年」
潭州で過ごしていた晩春のころ、杜甫は湖南採訪使の宴席で旧知の李亀年(りきねん)と偶然に出会いました。李亀年は玄宗の宮廷で著名な宮廷歌手でした。その有名人が江南の果てともいうべき潭州に流れてきているとは、杜甫の予想もしないことでした。
杜甫は四十五年前、まだ十五歳のときに洛陽の岐王李範(りはん)や秘書監崔滌(さいでき)の屋敷で李亀年の歌を聞いています。杜甫は平和で希望に満ちていた昔のことを回顧しながら、「落花の時節 又君に逢う」と流離の人生の悲哀を詠います。
「 聶耒陽以僕阻水書致酒肉 療饑荒江詩得代懐興尽本 韻至県呈聶令陸路去方田
駅四十里舟行一日時属江 漲泊於方田」」
李亀年と会って間もない夏四月、長沙で兵乱が発生しました。湖南兵馬使の臧?(ぞうかい)が潭州刺史崔?(さいかん)を殺して叛乱を起こしたのです。杜甫は乱を避けて北へ行ってもよかったかも知れないと思うのですが、向かった先は南で、衡州に避難しました。 衡州に着いた杜甫は、さらに湘水支流の耒水(らいすい)を遡って?州(湖南省?県)に行こうとしました。?州(ちんしゅう)で録事参軍をしている舅父の崔偉(さいい)を頼ろうと思ったのでしょう。ところが衡州から80kmほど遡った方田駅(ほうでんえき)で洪水に遇い、舟を進めることができなくなりました。
杜甫は五日間も食事ができないほどの窮状におちいりますが、耒陽県(湖南省耒陽県)の県令の聶(じょう)氏が聞きつけ、食糧を届けて救ってくれました。その経緯は詩の長文の題詞につづられています。
急場を救ってくれた県令に感謝するため、杜甫は方田駅から北へ20kmほどの陸路をたどって耒陽県の県衙(けんが)へゆき、みずから詩を贈って礼を述べたようです。 詩題の長さは、よほど嬉しかった心境を表しています。
「迴 棹」
方田駅で洪水に遭ったために、杜甫は?州(ちんしゅう)に行くことを諦めます。舟をかえして衡州にもどり、そこに留まりました。衡州にいた夏のあいだに、杜甫は北への「迴棹」(かいとう)を決意したようです。
舟中に、溜まるのは酒の空瓶だけだと嘆きます。体も洗えず、雨漏りで濡れる病気の体です。食事もあまり咽喉を通らなくなり、「蓴滑」を添えて流し込むありさまです。
「風疾舟中伏枕書懐三十六韻 奉呈湖南親友」
この詩は『杜少陵詩集』の最後に置かれており、湖上をゆく杜甫の絶筆とされています。衡州で「迴棹」を決意した杜甫は、ほどなく潭州の兵乱も収まったので、衡州から潭州に移ると、秋のあいだは潭州にとどまって北航の準備をととのえました。世話になった知友に別れの挨拶をし、潭州を船出したのは冬のはじめでした。
詩は舟中に病気の身を横たえながら、潭州の親友に贈ったものです。
病の身に薬を飲み、杖の援けを借りながら、杜甫の反省はつづきます。一度つまずいた身が恰好よく歩こうとしても、結局は知己の親切に頼る生活です。。特に潭州では多くの友人に快く迎えられ、そのことに重ねて感謝しています。昌江の城市に斐隠(はいいん)という名医がおり、病が重くなった杜甫は斐隠の治療を受けるために昌江の町の岸辺に舟を繋ぎ、停泊中に舟中で家族に看取られ、没した。大暦五年(770)の冬、享年五十九歳でした。
杜甫は岳陽に近い湖岸で亡くなり、岳陽に仮埋葬されたというのが通説でしたが、1980年代に研究がすすみ、杜甫は洞庭湖の中ほどから東へ汨羅水を遡り、汨羅水の中流北岸にある昌江(湖南省平江県)で亡くなったという説が有力になっています。平江県大橋郷小田村に高さ1m余の封土で覆われた墓があり、「唐左拾遺工部員外郎杜文貞公之墓」と刻んだ墓碑が建っているそうです。「文貞公」というのは元の順帝が至正二年(1342)に追贈した送り名であるといいます。付近に七百三十一人いるという杜姓の者は、春秋二回、杜甫墓を清め、いまも例祭をつづけているそうです。
官をやめてからの杜甫は、
社会詩人であることをやめて、詩を芸術作品として高めるために、いろいろと様式のくふうをし、中国詩の可能性の極限に近いところまでの追究を試みた。
杜甫が後世「詩聖」をもってあがめられるのは、実にこの点にある。
杜甫の一生のうち
在官中はすぐれた社会詩人として、また官をやめて放浪の旅に出てからは、すぐれた芸術詩人として、後世の詩人に限りない刺激を与えたのであった。
● 杜甫の詩
